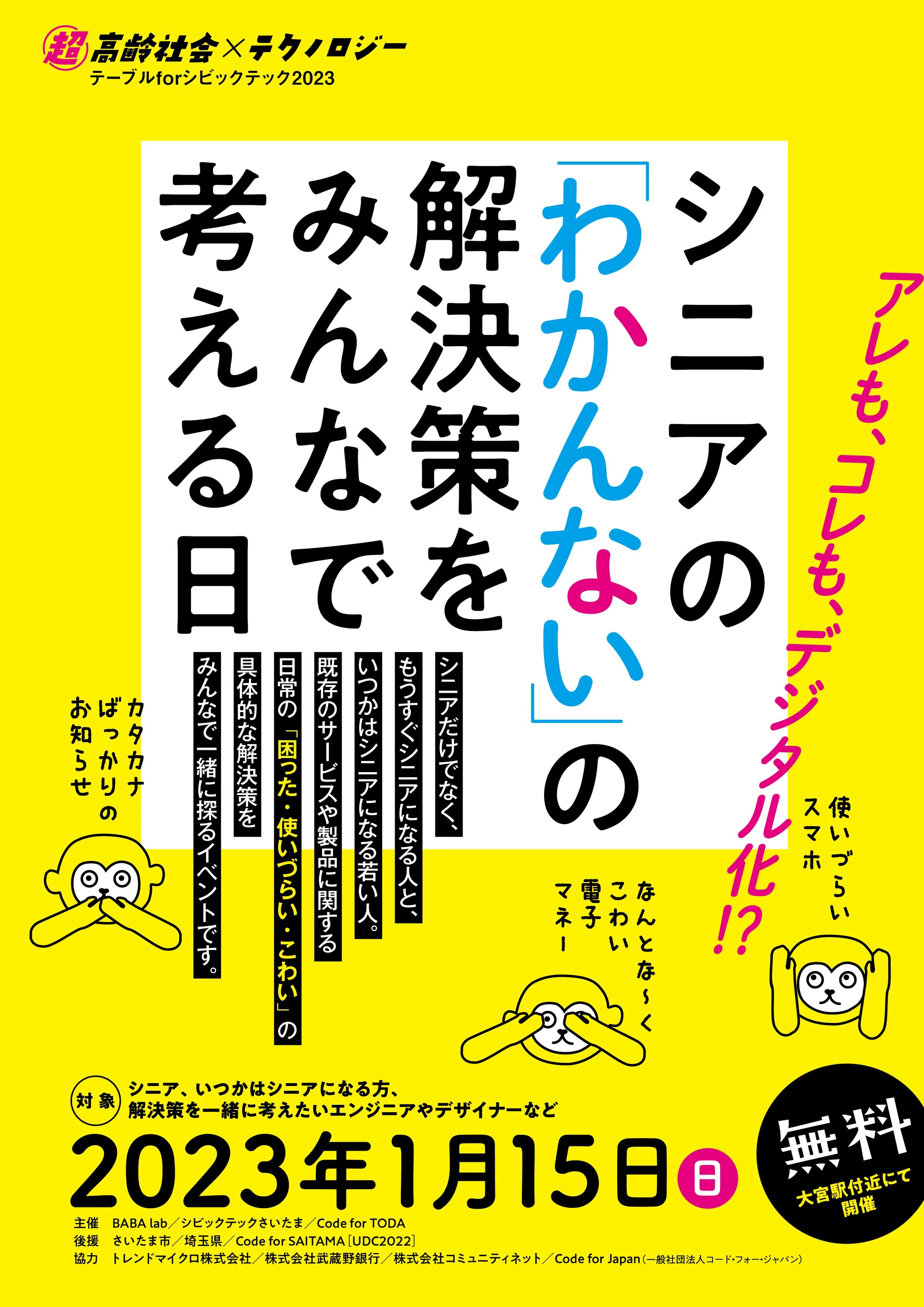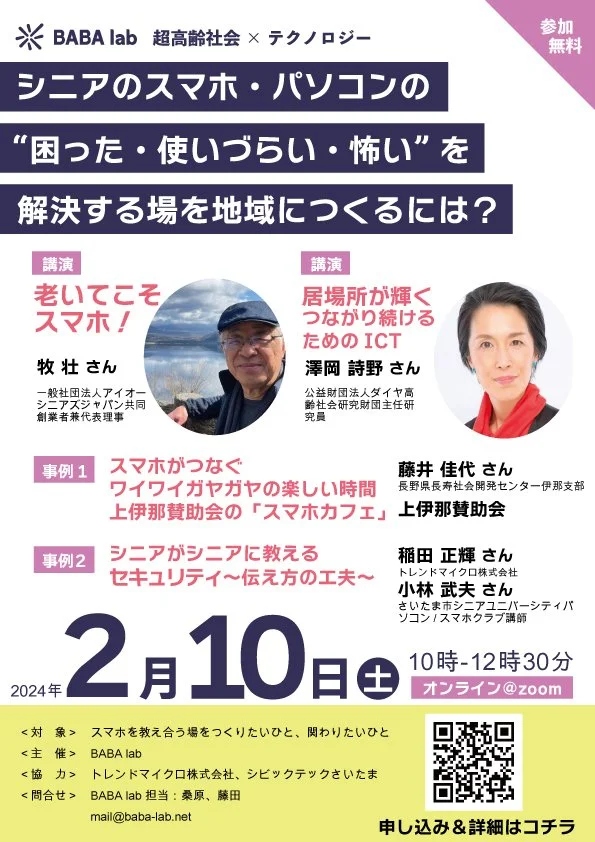『スマホのわからないを解決したい』プロジェクト イベント開催など
このプロジェクトでは、シニアの「わかんない」を集めるイベントを開催したり、先生と生徒の関係性ではなく、仲間同士でスマホのわからないことを教えあえる“ちょっとした場づくり”の勉強会を開いたり、場所をつくりたい人をサポートしたりしています。
□協力・連携先
シビックテックさいたま
Code for TODA
Code for Japan(一般社団法人コード・フォー・ジャパン)
トレンドマイクロ株式会社
武蔵野銀行
□企画の背景
・スマホや電子マネーなど、世の中で“便利”と言われているサービスに“不便さ”を感じるシニアが多数いる
・操作や使い方がわからないときに気軽に聞ける場所がない
キャリア会社の相談会・勉強会:ハードルが高い、新しいスマホを勧められそうなど
自治体の開催する講座:自分のレベルに合わない、開催の頻度が低い
家族や友人:何回も聞きづらい、聞くのが恥ずかしい など
<取り組みその1>
リアルイベントの開催
『シニアのわかんないの解決策をみんなで考える日』を実施
さいたま市内で<超高齢社会×テクノロジー>がテーマのイベントを実施。シニアだけでなく、もうすぐシニアになる人と、いつかはシニアになる若い人と、みんなで一緒に、既存のサービスや製品に関する「困った・使いづらい・怖い」を洗いだし、具体的な解決策を探るイベントで、約80名の方が参加しました。
■イベント内容
・超高齢社会×テクノロジーの現在
・グループワーク「困った・使いづらい・怖い」をあらいだす
・「困った・使いづらい・怖い」の共有
・グループワーク「解決策を考える」
・解決策の発表
・まとめ、今後のスケジュール
★当日の様子動画公開 ※ 約30分ダイジェスト版
https://youtu.be/3lQ7uWLB7RM
★ワークショップ「しゃべりましょう」で集まった約400枚の「困った・怖い ふせん」をテキスト化https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPYjvx_a1zpqGXhUL1YPVn_R6VELSyTarfXAZJnrXWc/edit?usp=sharing
※オープンデータ
<取り組みその2>
オンラインイベントの実施
『シニアのスマホ・パソコンの“困った・使いづらい・怖い”を解決する場を地域につくるには?』
スマホが普及し、連絡や買物など生活が便利になった一方で、苦手に感じる高齢者も増えており、「スマホのことを気軽に聞ける場がほしい」「学び合える友だちがほしい」など、地域のなかで支え合える場の必要性もが高まっています。イベントでは、『スシニアのスマホ・パソコンの“困った・使いづらい・怖い”を解決する場を地域につくるには』をテーマに、場づくりのコツや課題などを実践者の方に伺い、理想の場について考えました。
■スピーカー 老いてこそ、スマホ!
牧 壮 さん
シニアへネット活用を呼びかけるエバンジェリスト。一般社団法人アイオーシニアズジャパン共同創業者兼代表理事。著書に「老いてこそ、スマホ 年を重ねて増える悩みの9割は、デジタルで解決する 老いに親しむレシピ」(2023年主婦と生活社)などがある。
■スピーカー 「居場所が輝く、つながり続けるためのICT」
澤岡 詩野 さん
公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員。専門領域は老年社会学、高齢社会の地域づくり。人生100年を豊かにするための、家庭でも職場でもない3つ目の居場所の在り方を明らかにすべくフィールドワークに力を注いでいる。
■事例紹介1 「スマホがつなぐワイワイガヤガヤの楽しい時間」
藤井 佳代さん(長野県長寿社会開発センター伊那支部)
上伊那賛助会
■事例紹介2 「シニアがシニアに教えるセキュリティ~伝え方の工夫~」
稲田 正輝さん(トレンドマイクロ株式会社)
小林 武夫さん(さいたま市シニアユニバーシティパソコン/スマホクラブ講師)
★当日の様子動画公開
https://youtu.be/KV9-WJa9QaA
□ポイントと効果
(1)参加のハードルを低くする
リアルイベント『シニアのわかんないの解決策をみんなで考える日』では、わらかないこと=恥ずかしいという気持ちが強いシニアに対して、皆さんの「わからない!」という声がサービスや商品の改善につながることを丁寧に伝え、お菓子を食べながら、 “おしゃべり”のなかで、臆せずに「困った・使いづらい・怖い」を話せる場づくりを心がけた。
(2)地域のエンジニアなど“つくれる人”を巻き込む
イベントには、地域で“シビックテック活動”(地域の課題をテクノロジーによって使って解決する活動)に参加するエンジニアやプログラマーのほか、IT企業の方にも多く参加していただいた。イベント後も、サービスや商品の改善や開発に取り組んでもらえるよう促した
(3)集めたデータを公開する
リアルイベント『シニアのわかんないの解決策をみんなで考える日』のワークショップ「しゃべりましょう」で集まった約400枚の付箋をテキスト化、分類分けをしてオープンデータとして公開した。公開されたデータを使って大学での授業を行ったり、AIでの解析を行ったりするという活用事例があった